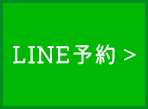保育士試験にチャレンジしました
投稿日:2025年5月6日
カテゴリ:勉強会報告
こんにちは
吹田 いぬい歯科クリニック 院長の乾です。
実は院長 先日、保育士試験を受験してきました!

今回は完全に独学での挑戦。本とYouTube、そして市販の過去問をフル活用しながら、仕事の合間に少しずつ3ヶ月ほどかけて準備をしました。…が、正直、覚えることがとにかく多い!
途中何度も「わからない〜!」と投げ出したくなりました。(笑)
保育士試験は2日間で全9科目一つひとつの内容が濃く、簡単なものではありませんでしたが、その分しっかり学べたことは今後の歯科臨床にも子育てにも大きな財産になると感じています。
ここでは、試験科目を簡単にご紹介しながら、感じたことを綴ってみます。
① 保育原理
日本の保育の目的・理念、保育所保育指針の構成など。保育の本質を学べたことで、自分がなぜ子どもに関わりたいのかを再確認できました。
② 教育原理
教育制度や教育基本法、学校教育との違いなど。保育と教育の接点を理解する中で、「育てること」の意味を考えさせられました。
③ 社会的養護
児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設など、社会的に保護が必要な子どもたちを支える仕組みを学びました。知らない世界が多く、とても勉強になりました。
④ 子ども家庭福祉
児童福祉法や母子保健法、児童相談所など家庭を支える制度の基礎。地域での連携が大切だと実感しました。
⑤ 社会福祉
福祉の原理、社会保障制度、高齢者や障害者福祉との関連など広範な内容。歯科医療でも地域包括支援に関わる視点として重要です。
⑥ 子どもの保健
乳幼児の疾病、予防接種、事故予防など。歯科とも直結する知識が多く、0歳からの健康管理への理解が深まりました。
⑦ 子どもの食と栄養
栄養素、離乳食、食育の基本、アレルギー対応など。赤ちゃんの口腔機能や食べる発達をサポートする視点が身につきました。
⑧ 子どもの発達心理学
0歳〜思春期までの発達過程、愛着形成、知能や感情の発達。歯科での子どもの対応や保護者支援にも応用できる知識ばかりでした。
⑨ 保育実習理論
音楽(楽譜問題)、造形(描画の知識)、言語(お話づくり)など、実践的な力を問われます。
馴染みがない音楽問題には四苦八苦でした(笑)。
保育士試験の合格率は毎年15~20%程度で、わりとハードルが高い国家資格です。簡単には取れない分、得られる知識と自信はとても大きいものでした。
実は、私が保育士資格を取ろうと思ったのは、当院をもっと「子どもに強い歯科医院」にしていきたいという思いがあったからです。来年からは、「0歳からの歯みがき教室」をスタート予定です。対象は4ヶ月の赤ちゃんとその保護者。歯が生える前から口に触れる習慣をつけることが、将来の歯みがき嫌いの予防につながると考えています。
また、試験に行くために医院を留守にした際、スタッフのみんなが本当に快く支えてくれて、医院をしっかり回してくれたことにも心から感動しました。応援してもらえる環境があること、そのありがたさを改めて感じた日でもありました。
将来的には、地域に根差した保育園の開設も視野に入れています。保育士として、歯科医師として、そして一人の親として、子どもと家族の健康を多方面から支えられる存在を目指していきます。
この経験を通じて、学びに終わりはないことを実感しました。そして、資格はゴールではなく「新しいスタート」です。今後も地域の皆さまに信頼していただける医院づくりを目指して、日々前進していきたいと思います。

■ 他の記事を読む■